「最近、公務員の早期退職をよく聞くし、周りの同僚でも辞める人が増えている。実際にはどの程度増えているのだろうか」
「自分もこの職場でこの先も続けることは考えられない。けれど、公務員を辞めて民間に転職できるのだろうか」
このように公務員離れが注目されるようになり、自分ごととして捉えるようになっている人もいるのではないでしょうか。
安定した職業の代名詞とされてきた「公務員」。
しかし近年では、早期退職や転職を選ぶ公務員が増えているといわれています。
この記事では、公務員離れの現状やその理由、民間企業の優位性、実際の退職理由までを具体的に解説します。
本記事でわかること:
- 公務員離れの現状やその理由
- 公務員よりも民間企業が選ばれるようになった背景
- 元公務員のリアルな退職理由
僕自身も、約15年間を都道府県庁で過ごす中で、続けることに疑問を抱き、転職活動を経て最終的に民間企業へ転職しました。
本記事を読むことで、公務員から転職することも現実的な選択肢として考えられるようになるでしょう。
公務員離れの現状
「公務員離れ」とは、国家、地方を問わず、公務員を目指す人が減ったり、採用された若手職員が早期に退職したりする現象が深刻化している状況を指します。
かつては「安定した職業」の代名詞とされていましたが、近年はその魅力が薄れつつあると考えられています。
離職・早期退職の増加
総務省の調査や各研究機関の報告によれば、2022年度の地方公務員の普通退職(自己都合)者数は12,000人を超え、5年前と比べて約46%増しています。
さらに、全国の自治体のうち6割以上が「若手の離職率が上昇傾向にある」と認識しており、公務員離れが一時的な現象ではなく、構造的な課題であることがうかがえます。

採用競争率の低下
総務省の調査によると、2023年度の地方公務員採用試験の競争率は4.6倍と過去10年で最低水準まで下がりました。
受験者数そのものも減少傾向にあり、若者から「公務員を目指す」動きが弱まっています。
一方で国家公務員は2025年度の申込者数が3年ぶりに増加するなど、分野によって温度差があるのも特徴です。

なぜ公務員離れ・公務員の早期退職が起きているのか
長時間労働と業務負担の増加
地方自治体や学校現場では、住民対応や福祉業務、教育の多様化により業務量が膨れ上がっています。
行政職では、月45時間以上の時間外勤務をする職員の割合がじわじわ増加しており、「定時に帰れる」という従来のイメージからかけ離れた現状です。
また、教員は在校時間が長く、病休や採用難にも直結しています。
仕事の魅力・キャリア観の変化
若手世代を中心に「安定よりも成長」「組織よりも専門性」を重視するキャリア観が広がっています。
異動が頻繁で専門性を積みにくい公務員の仕組みに違和感を覚え、早期に民間へ転じる人が増えています。
特に30代後半〜40代では「このまま定年まで続けるべきか」という迷いが強まり、転職を検討する大きな要因となっています。
民間との処遇競争
人事院はここ数年、初任給の大幅引き上げや月例給の増額を勧告しており、これは裏を返せば「民間との給与差で採用や定着が難しくなっている」ことを示しています。
実際、優秀な人材ほどより高い報酬や柔軟な働き方を求めて民間へ流出しているのが現状です。
住民対応における“カスハラ”の増加
市役所や役場の窓口では、利用者からの理不尽な要求や暴言といった「カスタマーハラスメント」が問題化しています。
全国の自治体調査では3人に1人の職員が経験ありと回答しており、精神的負担から退職を考える職員も少なくありません。
東京都ではカスハラ防止条例が施行されるなど、改善に向けた動きも始まっています。
元公務員のリアルな退職理由
希望するキャリアを形成できない
退職を意識し始めたきっかけは、異動希望がなかなか通らなかったことでした。
僕にはスキルを伸ばしたい専門分野がありましたが、一度そこから離れるとなかなか元の部署に戻れませんでした。
僕がいた自治体では平均2〜3年で異動があり、業務内容が大きく変わるのは当たり前です。
比較的希望する部署に配属される方でしたが、徐々に自分のキャリアを自分の意志で形成できない現実に直面。
「自分の望むキャリア形成が難しい」と感じたことが、モチベーション低下につながったりました。
議会対応などでの拘束
議会期間は、関連する質問が出ると答弁作成のため深夜まで帰れないことはよくありました。
あるときは深夜に地震が発生し、電車運行がない中、庁舎まで2時間以上かけて歩いて出勤したこともあります。
独身の頃はまだ耐えられましたが、子どもが生まれると事情は一変しました。
子どもがいれば、早く帰って子どものお世話をしなければなりません。
また、地震時に家族をおいて公務を優先する立場ということにも違和感。
仕事をする上で、育児との両立が最も重要になり、理想と現実の働き方にギャップを感じるようになっていきました。
パワハラ気質の同僚・人間関係
退職の決め手となったのは、異動先にパワハラ気質の職員がいたことです。
徹底的なダメ出しや理不尽な仕事の押し付けに悩まされました。
当時は子どもが生まれたばかりで、このままでは精神的に追い込まれ、つぶれてしまうと感じました。
結果的に退職を決意するきっかけとなり、ピンチをチャンスに変える出来事だったとも言えます。
少なくとも僕がいた自治体には、人に圧をかけ、仕事を押し付けることが染み付いてしまった人が多くいたように感じます。
収入面は理由でない
収入アップは一般的に転職の上位の理由ですが、僕の場合は違いました。
係長職としての収入は、民間の大手企業に勤める大学同期と比べると劣りますが、世間的にまずまずの収入だったからです。
そのため、転職では「収入を下げない」という条件を付けたことにより、転職先の選択肢を狭める結果ともなりました。
公務員よりも民間企業が選ばれるようになった背景
ワークスタイルと労働環境の変化
- 長時間労働と激務のイメージ: 公務員の職場、特に中央省庁や一部の自治体では、依然として長時間労働や激務のイメージが強く、これがワークライフバランスを重視する若者にとって大きな懸念材料となっています。
- デジタル化の遅れ: 民間企業と比較して、行政機関のデジタル化(DX)の遅れが指摘されています。紙文化の根強さや古い情報システムの使用は、デジタルネイティブ世代にとって非効率的で魅力に欠ける職場環境と映ります。
- メンタルヘルス不調の増加: 職場の対人関係や困難な業務への対応による、公務員のメンタルヘルス不調での休職者が増加傾向にあることも、敬遠される一因です。
評価・キャリア形成に対する価値観の変化
- 成果主義・実力主義への志向: 若者の間で、年功序列型の賃金体系や評価システムよりも、自分の能力や成果が給与や昇進に直接反映される実力主義・成果主義を志向する人が増えています。この点で、業績や結果が分かりやすい民間企業が魅力的に映ります。
- 自己成長・専門性の重視: 定期的な異動(ジョブローテーション)が原則の公務員に対し、「自身の専門性や興味に基づいた仕事」や「自己成長」の機会を重視する若者が増えています。民間企業では、ジョブ型雇用や専門性の高い職種が増加しており、個人のキャリア形成の自由度が高いと認識されています。
- 副業への関心の高まり: スキルアップや副収入を目的に副業に関心を持つ若手が多い中、公務員は原則副業が禁止されており、これも民間企業との差別化要因となっています。
公務員の安定性の相対的な低下
- 給与水準の長期的な変化: 過去には民間企業よりも高かったとされる給与水準や福利厚生が、財政難や行政改革の影響で相対的に低下した時期がありました。現在も高水準ではあるものの、民間企業の好業績企業との比較では差が縮まっています。
- 「安定」以外の価値の重視: かつて公務員の最大の魅力であった「雇用の安定」は、現代の若者にとって「やりがい」「成長」「自由な働き方」といった他の要素ほど絶対的な魅力ではなくなりつつあります。
採用スケジュールの問題
- 民間との試験日程の乖離: 民間企業の就職活動が早期化する一方で、公務員試験の主要な日程が依然として遅い時期(6月頃)に集中しているため、「公務員試験一本に絞るのは不安」、「早く進路を決めたい」と考える学生が、早期に内定が出る民間企業を選びやすくなっています。
公務員離れ・公務員の早期退職に関するよくある質問
Q1. 本当に公務員の早期退職は増えているのですか?
はい、事実として増加傾向にあります。
国家総合職では10年未満で辞める職員が2023年度に200人を超え、過去10年間で上昇しています。
地方自治体でも自己都合による退職(普通退職)が一定数見られ、「安定」一辺倒ではなくなってきています。
Q2. なぜ若手の公務員が辞めてしまうのですか?
大きな理由は次のとおりです。
- 長時間労働:法定上限を超える時間外勤務が常態化する部署もある。
- 処遇格差:民間企業の賃上げが進む中、給与・昇進スピードが相対的に見劣りする。
- やりがいの低下:非効率な業務や政治的制約により、成果を実感しにくい。
つまり「安定しているけれど未来を描けない」と感じる若手が増えています。
Q3. 公務員試験の志望者も減っているのですか?
はい。国家公務員試験の申込者数は長期的に減少しており、地方自治体でも倍率が低下しているケースが目立ちます。
優秀な人材が集まりにくい「人材確保難」の状況は、組織全体に影響しています。
Q4. 自己都合で早期退職すると退職金は減りますか?
大幅に減ります。
「国家公務員退職手当法」では、自己都合退職で勤続10〜24年の場合、退職手当の調整額が原則「2分の1」になるなど、定年退職より大幅に減額されます。
勤続9年以下は調整額0。地方も条例でおおむね同趣旨です。
Q5. 定年引上げはどう影響していますか?
2023年度から段階的に定年が65歳に引き上げられました。
移行期では60歳前でも定年退職扱いに準じる特例があり、年齢構成や退職時期の偏りが起きています。一方で「65歳まで働き続けることは現実的に厳しい」と感じ、早期退職を選ぶ層も出ています。
Q6. 地方自治体の現場はどうなっていますか?
自治体職員数は長期的に減少〜横ばいですが、社会保障や福祉など住民サービスの需要は拡大。
その結果、一人あたりの業務量が増え、残業の増加やメンタル不調による離職にもつながっています。
Q7. 改善の動きはありますか?
はい。最近では国家公務員の男性育休取得率が8割を超えるなど、働き方改革は進みつつあります。
ただし部署や自治体ごとの差が大きく、継続的な改善が必要となっています。
まとめ
公務員離れや早期退職の増加は、もはや一部の人だけの話ではなく、誰にとっても身近な課題となっています。
「このまま定年まで働けるのか」「今の環境でキャリアを積み上げられるのか」と感じるのは決してあなただけではありません。
ただ、不安を抱えたまま行動しなければ現状は変わりません。
僕自身も、公務員として働き続けることに疑問を抱きながらも、転職エージェントを活用して情報を集めたことで、一歩を踏み出すことができました。
もし少しでも「転職」という選択肢を考えているなら、まずは無料で登録できる転職エージェントに相談してみるのがおすすめです。
専門のキャリアアドバイザーに話すだけでも、あなたのキャリアの可能性がぐっと広がります。今のモヤモヤを行動に変えるかどうかが、これからの人生を左右します。
ぜひ今日から、小さな一歩を踏み出してみませんか。
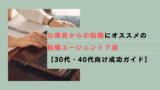
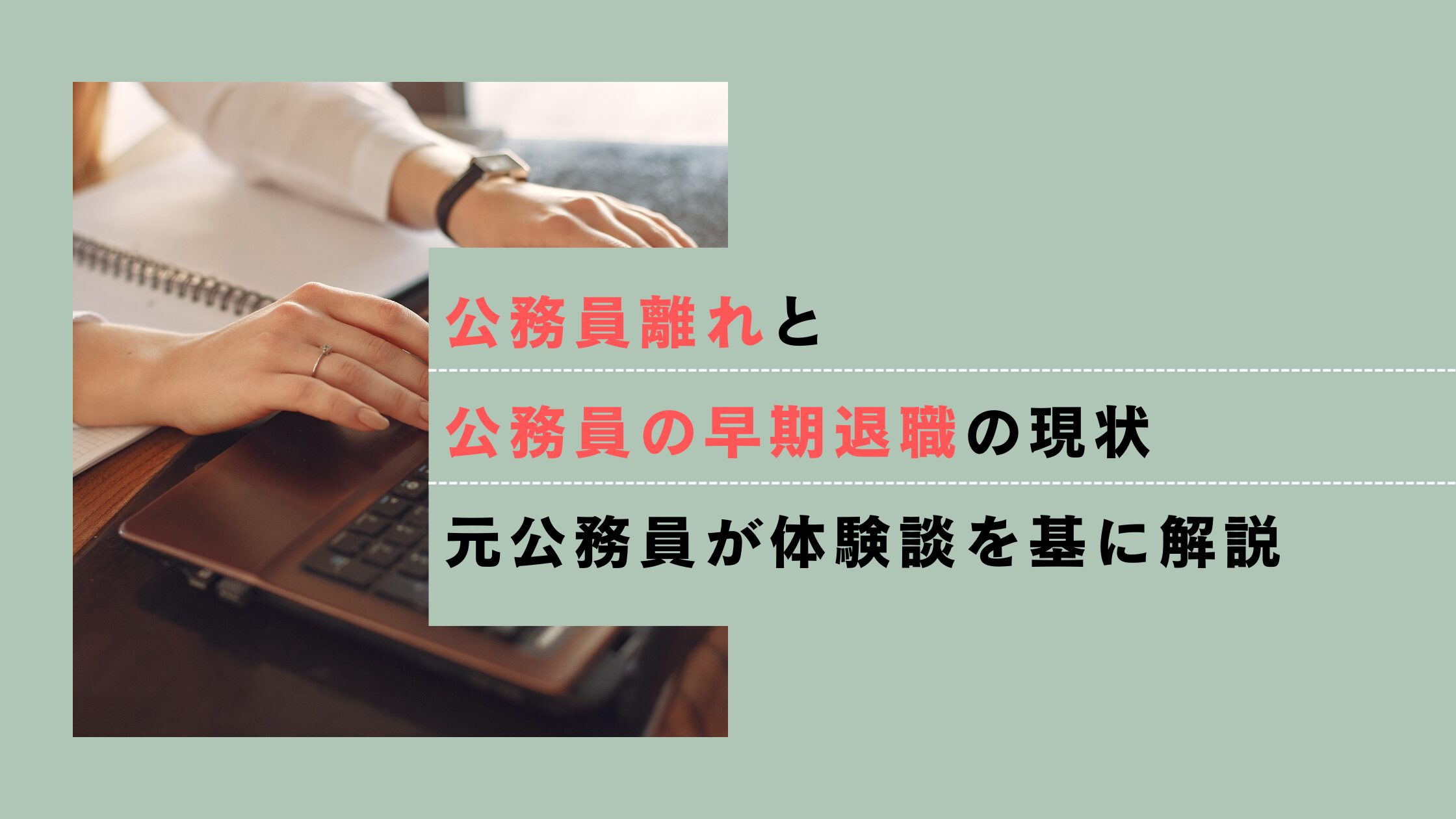
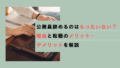

コメント