「今、勤めている自治体の職場環境や組織風土が合わない。けれど、民間企業に転職したいとも思わないので、公務員の仕事は続けたい」
「市役所に勤めているが、窓口業務が多いし、ケースワーカーも自分には合わない。広域の政策に関われる都道府県庁へ挑戦したい」
公務員が転職を考えたとき、民間への転職は敷居が高いけれど、これまでの経験をフルに活かせる公務員への転職であれば、視野に入るのではないでしょうか。
実は、公務員の経験を活かして別の自治体や機関へ転職することは十分に可能です。
しかも、キャリアアップ・ワークライフバランス改善・地元回帰など、目的に応じた多様な選択肢があります。
本記事では、「公務員から公務員の転職」について、転職パターンや筆者の身近な成功実例を解説します。
この記事でわかること:
- 採用ルート(一般採用・経験者採用)
- 公務員から公務員への主な転職パターン
- 実際の成功事例
この記事を読めば、「公務員から公務員への転職」がどういったものか網羅的に理解し、転職のイメージが明確にできるようになり、失敗しない転職へとつながります。
筆者自身、民間企業や公務員への転職を書籍やWEB、友人知人から徹底的に情報収集を行い、アラフォーながら初めての転職を狙い通りに成功させました。
ぜひ、参考にしてください。
公務員から公務員への主要な採用2パターン
① 一般採用(再受験)による転職
最もオーソドックスなのが、希望先の採用試験を再受験する方法です。
年齢制限の範囲内であれば、同じ公務員でも別自治体へ転職することが可能です。
たとえば、都道府県庁→市役所、政令市→特別区などへの転職は毎年一定数あります。
ただし、受験区分や年齢制限が異なるため、必ず各自治体の募集要項を確認しましょう。
受験日は毎年6〜9月に集中する傾向があるため、早めの準備がカギです。
② 経験者採用(社会人採用)を利用した転職
多くの自治体が「社会人経験者採用」「キャリア活用採用」を実施しています。
これは、民間や公務員としての職務経験を活かして採用する制度です。
試験内容は、筆記(SPI3など)・プレゼン・面接が中心で、 新卒採用のような教養・専門試験がないケースも多いのが特徴です。
“公務員経験も社会人経験としてカウント”されるため、現職のまま別の公務員試験を受けられるチャンスがあります。
公務員から公務員への転職5つパターン
公務員から公務員への転職には、目的に応じた多様なルートがあります。
ここでは代表的な5つの転職ルートを紹介します。
自分の働き方や価値観に合うルートを見つける参考にしてください。
① 都道府県庁 → 市役所への転職
地域密着型の仕事にシフトしたい人におすすめ
都道府県庁で広域的な政策や調整業務を経験した後、 より現場に近い「市役所」へ転職するケースです。
主な採用方法:
- 一般採用(再受験)
- 社会人・経験者採用枠
特徴・ポイント:
- 「地域に直接貢献したい」「住民対応をやりたい」といった志望動機が通りやすい。
- 都道府県での行政経験は、市役所にとって“即戦力”と見なされやすい。
- 前歴加算によって、給与はある程度維持される傾向。
注意点:
- 小規模自治体ほど採用人数が少なく、倍率が高い。
- 異動範囲は狭くなるが、業務範囲は広がる(総合行政職的な動き方が多い)。
② 市役所 → 都道府県庁への転職
キャリアアップ・政策志向型の人に人気
市役所で現場業務を経験し、広域行政や政策立案に関わりたい人が選ぶルートです。
主な方法:
- 職務経験者採用
- 一般採用試験(再受験)
特徴・ポイント:
- 都道府県庁は「市町村支援」「補助金管理」「広域計画」などの上位調整機関。
- 市役所の実務経験を、「現場感覚のある人材」としてアピールできる。
- 採用面接では「現場経験をどう政策に活かすか」を明確に伝えることがカギ。
注意点:
- 競争率が高め。
- 試験レベル(専門科目や論文)がやや難しいため、早期対策が必要。
③ 都道府県庁 → 国(国家公務員)への転職
より広い視野・政策レベルで働きたい人へ
国家公務員への転職は、人事院の経験者採用試験などを通じて行われます。
内閣人事局の中途採用サイトでも、中央省庁の公募情報が公開されています。
主な方法:
- 国家公務員「経験者採用試験」
- 各省庁の中途採用(キャリア職・係長級)
ポイント:
- 都道府県での行政経験は「現場感覚を持つ政策人材」として評価される。
- 採用後は東京勤務が中心だが、政策形成・法律立案など国レベルの業務に携われる。
注意点:
- 採用倍率が高い(人気官庁では数十倍)。
- 都道府県勤務のスキルを“政策課題にどう転用できるか”を面接で明確に説明する必要あり。
④ 国(国家公務員) → 都道府県庁・市役所への転職
地域や住民に近い立場で働きたい人に人気
ここ数年で増えているのが、中央省庁から地方自治体へ転職するケースです。
過重労働・転勤負担・家庭事情などを背景に、ワークライフバランス重視型の転職として注目されています。
主な方法:
- 都道府県・市役所の「経験者採用枠」
- 一般採用(再受験)
ポイント:
- 国家公務員経験は地方自治体で高く評価される(特に財政・企画・法務系)。
- 政策知識や折衝能力を“現場で活かせる人材”として歓迎される。
- 近年は「国→地⽅」のキャリアチェンジを支援する制度も拡充。
注意点:
- 採用試験では「なぜ国を辞めて地方へ?」という質問が必ず出る。
- 給与体系が異なるため、初年度は号給調整で一時的に減ることもある。
⑤ 市役所・都道府県庁 → 他自治体や公的法人への転職
ライフスタイル・地元回帰を重視するケース
- Uターン・Iターン転職:地元の自治体へ戻る。
- 特別区職員(東京23区)への転職。
- 独立行政法人・公益法人への転職。
ポイント:
- 前歴加算の取り扱いは団体により異なる。
- 公務員経験が活かせる。
- 「家庭・地域との両立」「地元貢献」を打ち出すと好印象。
公務員から公務員に転職した3つの成功実例|筆者の身近な体験談
①都道府県庁→区役所 Iさん(30代後半・女性/主任→主任)
都道府県庁で10年以上勤務していたIさん。
主任職として活躍していましたが、局間異動先で過度なプレッシャーから体調を崩し、休職することに。
休職期間中に「環境を変えて再スタートしたい」と区役所を受験し、見事合格。
現在は区役所の企画部門で政策立案や総合調整を担当し、無理のないペースで公務員としてのキャリアを続けています。
👉 ポイント:
都道府県庁から地域密着の区役所へ移ることで「働きやすさ」を重視した転職例です。
②市役所→都道府県庁 Kさん(30代後半・男性/係長→主任)
関西の政令市で係長職として働いていたKさん。
家庭の事情で奥様の地元・関東に移住することになり、都道府県庁に転職しました。
転職後は一時的に主任職からのスタートでしたが、着実に成果を重ね、管理職選考に合格。
現在は管理職として職場をまとめながら、家庭との両立も実現しています。
👉 ポイント:地域をまたぐ転職でも、キャリアアップを実現した好例です。
③独立行政法人→市役所 Kさん(30代後半・男性/係長→主任)
全国転勤のある独立行政法人に勤務していたKさん。
国への出向をきっかけに子どもが生まれ、「もっと家族と一緒にいたい」との思いから、自身と奥さんの同一の地元である市役所への転職を決意。
地元の自治体に採用され、現在は地域密着型の業務を担当。
生まれ育った街で、子育てと仕事を両立しながら公務員として活躍しています。
👉 ポイント:
全国転勤のある法人から、地元に根ざした市役所へ移る「ワークライフバランス重視型」の転職例です。
まとめ|「公務員から公務員への転職」は現実的なキャリア選択肢
「公務員から公務員への転職」は、決して珍しいことではありません。
むしろ、これまでの経験やスキルを最大限に活かせる“現実的で堅実なキャリアチェンジ”です。
都道府県庁から市役所、市役所から都道府県庁、さらには国や公的法人への転職など、自分の志向やライフステージに合わせた多様な選択肢があります。
実際に転職を成功させた人たちも、「職場環境を変えて働きやすくなった」「キャリアアップにつながった」「地元で家族と暮らせるようになった」と、それぞれの目的を実現しています。
とはいえ、自治体によって試験内容や前歴加算、募集時期は異なります。
まずは、希望先の自治体や機関の「経験者採用」情報を早めにチェックし、自分のキャリアや生活に合った転職ルートを見極めましょう。
✅ ポイント
・「民間よりも公務員内でキャリアチェンジしたい」人には最適な選択肢
・「現職の経験×希望する地域性」を軸に考えると失敗しにくい
・情報収集と早めの準備が、転職成功のカギ
今の職場で悩んでいるけれど、公務員という仕事そのものは続けたい——。
そんなあなたにこそ、「公務員から公務員への転職」は大きなチャンスです。
自分のキャリアを見つめ直し、より納得できる働き方を手に入れましょう。
▶️続いて読みたい
転職の流れを知りたい、転職の軸を定めたい、自分の強みを把握したい方については、こちらもご覧ください。
転職の流れ完全ガイド|30代後半が成功できる自己分析から退職までの8ステップ
公務員としての働き方に限界を感じたときに考える「転職の軸」【30代後半〜40代】
30代後半スキルがない公務員が転職で強みを見出す自己分析の方法【実例あり】
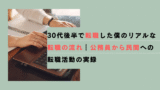
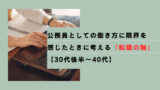
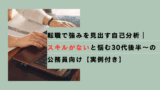
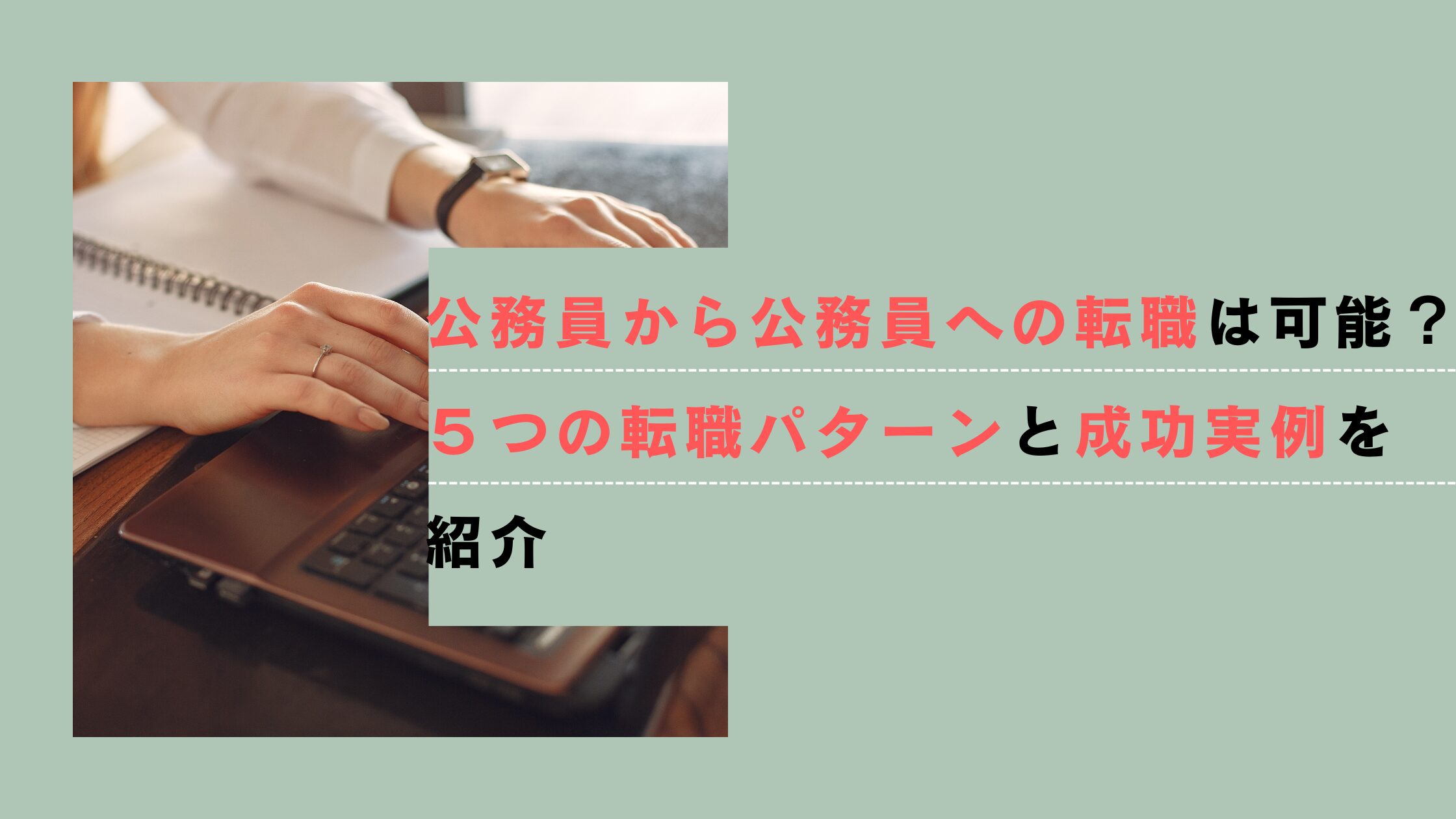


コメント