「最近は男性でも育休を取る人が増えているけれど、実際どれくらい取るのがいいの?」
そんな疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
本記事では、2度の育休取得経験をもとに「男性が育休をどれくらい取るべきか」、目安と判断ポイントを解説します。
結論:育休期間は2か月以上が目安
育休に「これが正解!」という明確な期間は存在しません。
育休期間は、「家庭の状況」、「職場環境」、「経済面」をふまえて検討することが大切です。
それでも目安としては、次のように考えると判断しやすくなります。
- 最低2か月以上
- 男性の育休取得の平均は1か月〜2か月程度
特に「産後すぐの時期」と「生後3か月ごろまでの育児が最も大変な時期」は、サポート体制を整えることが重要なタイミングになります。
これまで、僕は前職、公務員時代に第一子が生まれたとき、また転職後の現職で第二子が生まれたときの二度、育休を取得しました。
しかも、現職では、それまで男性社員の育休取得者はいない中での初めての育休取得。
そんな僕の実体験に基づいているので、ぜひ参考にしてください。
Ⅰ.育休期間を決める前に整理しておきたい3つのポイント
1. 家庭の育児体制
家族の状況により、パパのベストな育休期間は異なってきます。
育休をどれくらい取るべきかを考えるとき、まずは家庭の状況を整理しましょう。
チェックすべき項目は以下のとおりです。
- 周囲に祖父母など育児のサポートを頼める人はいるか
- 生まれてくるのは何人目か
- ママの職場復帰と子どもの保育園入園のタイミング
祖父母など育児のサポートを頼れる人がいるのか、いないのかは、まず重要です。
いなければ、当然、パパが家庭での育児の主戦力になる必要があります。
また、小さい子供がいる場合に、ママ一人で小さい子供と赤ちゃんのお世話をするのは大変。
ママの職場復帰の時期や子どもを保育園入園のタイミングといった今後の計画を立てましょう。
2.職場の制度と雰囲気
男性が育休を取得する際、会社の制度や理解ある職場かも考慮が必要となってきます。
会社の育休規程を読み解いて制度を把握するとともに、どれだけ取得しやすい職場環境かも確認して、現実的な期間を計画しましょう。
- 育休制度の有無と内容(就業規則を確認)
- 男性の育休取得実績があるか
- 上司や同僚の理解・協力は得られそうか
僕自身、現職では男性育休の前例がない中での取得でしたが、上司にしっかりと家庭の状況と想いを伝えることで、理解と協力を得ることができました。
3. 経済面(給付金制度)
- 育児休業給付金はいつ・どれくらい支給されるか?
- 半年間:手取り約67%支給 → 多くの男性が6か月未満に留める理由の一つ
- 7か月目以降:手取り約50%支給(上限あり)
我が家では2人目出産の際、半年で復職予定にして家計のシミュレーションをしました。
結果的に6か月育休を取り、経済的にも無理のない範囲で育児に集中できました。
Ⅱ.育休期間ごとの特徴とメリット
Ⅰ.で家庭や職場の前提状況を整理した上で、育休期間について考えていきます。
最低限をサポートしたいなら|2か月
- 産後6〜8週間(産褥期)をカバー
- ママの身体回復・育児スタートを支える
- 男性の育休取得期間平均(約46日)にも近い
出産後の産褥期(※)は、6〜8週間と言われています。
(※)産褥期とは、妊娠・分娩によって変化した身体が妊娠前の状態に戻るまでの時期のことをいい、産後約6~8週間のことを指します。
産後の体のダメージは、全治数か月の交通事故と同等のダメージといわれる程で、産後は無理をせず体を回復させることが重要になります。
この期間は、パパのサポートが必要不可欠。
2か月の育休であれば、この時期をしっかりカバーできます。
また、令和5年度の従業員1,000人超企業における男性の育休取得期間の平均46.5日です(厚生労働省「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」(速報値))。
このため、会社からの理解も得やすい期間と言えます。
しっかり関わりたいなら|3〜6か月
- 授乳・おむつ替えで24時間体制の時期
- ママの睡眠不足・負担ピークを支える
- 育児休業給付金67%支給の期間
子育てパパママからは、生後から3ヶ月までが子育ての一番大変な時期との声が多いです。
生後3か月ごろまでをカバーするには、3〜6か月の取得がオススメ。
この時期は、授乳やおむつ替えでほぼ24時間体制で、睡眠不足になりやすく、ママのワンオペであるとすると、体力・精神的負担もピークに達します。
また、育児休業給付金は、育休取得して半年間は給与の67%、半年から1年間までは50%となるので、収入面からも目安の一つとなります。
育児の楽しさも味わいたいなら|6か月以上
- 赤ちゃんが動き始める成長期をサポート
- 家族との深い絆を築ける貴重な時間
- ただし、職場復帰や収入面とのバランスも重要
6か月を超えると、赤ちゃんは手足を動かし始め、目を離せない時期に入ります。
しかし、赤ちゃんが笑う・動くなど成長を実感できる時期でもあります。
家族との深い絆を築ける貴重な時間となります。
もちろん、職場や収入面との兼ね合いもあるため、無理のない範囲での選択が大切です。
仕事の節目に合わせたいなら|上半期・下半期パターン
- 人事異動や事業年度の切り替えに合わせた復帰
- 4月、10月など区切りの良いタイミングで復職しやすい
人事異動が4月1日、10月1日にあるなど、上半期、下半期が仕事のスタートとして切りが良いような職場では、それに合わせて、3月末や9月末まで取得するというのも一案。
復職後の仕事の調整もスムーズになりやすく、周囲との調整もしやすくなります。
僕の実体験|2度の育休を通じて感じたこと
第一子のときは、最低限のサポートを意識して2か月間取得しました。
妻の体調を支えることができた一方、「もっと関わりたかった」との思いもありました。
そのため、第二子のときは、4月生まれだったこともあり、復職時期を10月に設定して約6か月間の育休を取得。
兄弟2人を同時に育てるという大変さはありましたが、その分充実感も大きく、育児に対する自信もつきました。
この経験から「迷うなら少し長め」をオススメします。
よくある質問(FAQ)
Q. 男性の育休、平均どれくらい?
→ 厚労省調査によると、平均取得期間は約1.5か月(46.5日)です。
Q. 経済的な心配があるけど大丈夫?
→ 給付金制度により、半年間は給与の67%、その後も50%が支給されます(上限あり)。
Q. 長く取りすぎると復帰が不安…
→ 上司・同僚との事前調整やタイミングを見計らえば、トラブルは防げます。
まとめ|育休は“未来の家族への投資”
育休期間に「正解」はありません。
しかし、家庭の状況や職場環境を踏まえたうえで、できるだけ納得のいく選択をすることが大切です。
迷っている方は、以下を一つの目安にしてみてください。
| 期間 | 特徴・目安 |
|---|
| 2か月 | 産褥期のママをしっかりサポート |
| 3〜6か月 | 育児の大変な時期に向き合える |
| 6か月以上 | 家族との深い絆を築ける |
| 上半期・下半期 | 職場復帰のタイミング調整に最適 |
何より、「パパが育児に関わること」が、子どもにとってもママにとっても、そしてパパ自身にもかけがえのない力になります。
▼関連記事:
「男性でも育休をそつなく取得するためのポイント7選」も、ぜひあわせてご覧ください。
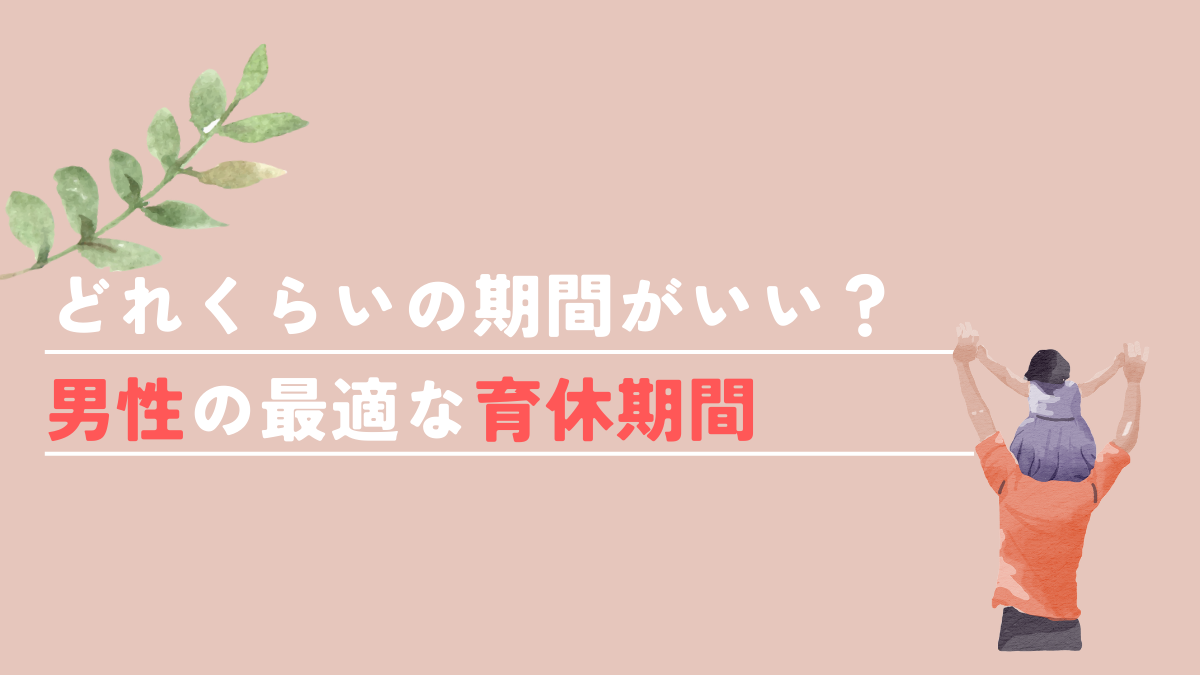
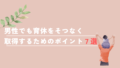

コメント