「転職を考えたいけれど、これまで公務員として働いてきて、これといったスキルがない」
「民間企業で通用する自分の強みが見えない」
公務員として長年働いてきた方ほど、こうした不安を抱きやすいものです。
しかし、実は“スキルがない”と感じているのは、自分の力を言語化できていないだけかもしれません。
本記事では、公務員が転職での「強み」を見い出す方法を解説します。
特に、公務員として長年勤めてきたが故に、いざ転職となるとスキルに自信を持ちづらい方に読んでほしい内容としています。
新卒から都道府県庁で約15年公務員として働き、実際に民間へ転職した僕の経験に基づいて紹介します。
【結論】自己分析により「強み」を言語化する
自己分析を通して得られる最大の成果は、自分の“経験価値”に気づき、それを「転職市場で通用する言葉」に変換できることです。
民間と公務員の違いを理解したうえで、自分が提供できる価値を知ること。
それが、転職成功への第一歩になります。
なぜ自己分析が必要なのか
自己分析なしの転職は、失敗のリスクが高いからです。
転職活動では、「何がやりたいか」「何ができるか」「どんな環境が合うか」を明確にすることが非常に重要です。
これが曖昧なままだと、内定はもらえてもミスマッチになり、結果として「転職して失敗した」と感じてしまうことが多くなります。
自己分析をしっかり行えば、
・応募する企業を選ぶ基準が明確になる
・履歴書や職務経歴書の自己PRに一貫性が出る
・面接でも自信をもって話せる
といった大きなメリットがあります。
自己分析の進め方:WILL・CAN・MUSTフレームで整理しよう
転職活動では、「WILL・CAN・MUST」の3つの観点で整理するのが効果的です。
| フレーム | 内容 |
|---|---|
| WILL | やりたいこと |
| CAN | できること(スキル・経験) |
| MUST | 求められること |
本記事では「CAN=できること」にフォーカスして深掘りします。
「WILL=やりたいこと」は最初に転職の軸で考えておきましょう。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
公務員としての働き方に限界を感じたときに考える「転職の軸」【30代後半〜40代】
また、「MUST=求められること」は企業や社会が求めていること。
求人票や募集要項で求められることを把握するのは必要ですが、あまり固執し過ぎないようにしましょう。
「スキルがない」と思っているあなたへ|「強み」を見つける4つの方法
「自分には売りになる専門性がない」
そういった方はポータブルスキルで勝負しましょう。
「ポータブルスキル」とは、職種の専門性以外に、業種や職種が変わっても持ち運びができる職務遂行上のスキルのことです(詳しくは厚生労働省HP参照のこと)。
ポータブルスキルを見つける4つの方法を示していきます。
① 実務経験を棚卸しする(業務年表を作る)
- 入庁から現在まで、どんな業務を経験したかを時系列で書き出す
- 担当したプロジェクト、関わった部署、成果や学びも記録
▶ 例:○年度〜×年度:○許可に関する審査業務(条例改正、相談対応含む)
② 褒められた・感謝された経験を振り返る
- 上司や同僚から感謝されたことは何か
- 「あなたにお願いして良かった」と言われた瞬間がヒント
▶ 例:住民説明会での説明が分かりやすいと上司から好評だった
③ 苦労せずにできることを探す
- 他の人が時間をかける作業でも、自分なら早く正確にできる
- 「なぜか頼られる業務」に注目する
▶ 例:複雑な法令文の読み解きと要点整理
④ 一番成果を出した業務経験を深掘りする
- 数字・具体的成果が出た経験は、あなたの「強み」を示す大きな材料
▶ 例:あるプロジェクトでリーダーを担当し、スケジュール通りに全工程を完了。関係者アンケートでは満足度90%という結果を出した。
公務員ならではの「転職市場で通用する強み」6選
私の公務員時代の経験を基に、民間企業でも通用する公務員ならではの強みを6つ挙げます。
① 調整力・折衝力
公務員は、庁内の関係者に限らず、地域住民や他の自治体、企業など、さまざまな立場の人々と関わる機会が多くあります。
それぞれの立場や主張を理解したうえで、対立しがちな利害を調整し、最適な解決策を導き出すスキルが求められます。
このような「異なる立場をつなぐ」調整経験は、民間企業でも重宝されるスキルです。
例えば、社内外の関係部署との折衝や、取引先との交渉においても活きる力と言えるでしょう。
② プロジェクト推進力
公務員の仕事の中には、予算やスケジュールが決められた年間計画に沿って、プロジェクトを遂行する業務も多くあります。
企画の立案から始まり、関係者との調整・説明・合意形成、さらには進行管理まで、一連の業務を責任を持って遂行する力が求められます。
限られた人員や予算、予期せぬ反対意見などに直面しても、粘り強く進めていく「やり抜く力」は、民間企業でも即戦力として高く評価される要素です。
③ 政策立案・制度設計の経験
企画部署で計画策定や制度設計に携わることがあります。
例えば、新たな行政計画の立案や、条例・規定の新設や改正などがそれにあたります。
このような業務では、多様な関係者の利害を踏まえたうえで、バランスの取れた制度設計が求められます。
特に、条例の新設、改正などは、国や関係団体との調整、パブリックコメント、議会対応といった複雑な手続きも伴います。
これらを丁寧に積み重ねた経験は、民間の制度設計や新規事業の立ち上げにも応用が可能です。
④ 柔軟性・対応力
公務員は、通常2〜3年ごとに異動があり、まったく異なる分野の業務に携わることも珍しくありません。
新しい業務を短期間でキャッチアップし、新たな人間関係を築いていく必要があるため、柔軟性と適応力が自然と養われます。
こうした経験を通じて、どんな環境にも素早く対応できる「柔軟性」が身につきます。
これは、変化の激しい現代のビジネス環境において、非常に大きな武器となります。
⑤ 正確な事務処理能力
公務員の業務では、許認可・契約業務・住民対応など、ミスが許されない正確さが求められる業務が多くあります。
その中で培われた「ミスを防ぐためのチェック力」や「先を予測してトラブルを回避する力」は、どの業種でも重宝されます。
加えて、正確性だけでなく、限られた時間でスピーディに処理する工夫を重ねてきた経験も、例えば民間での業務効率化や品質管理などに役立つでしょう。
⑥ 高いコンプライアンス意識
公務員は常に市民の厳しい目にさらされており、小さな行動でも誤解やクレームの対象になりかねません。
そのため、業務上の行動だけでなく、公私にわたって高い倫理観・コンプライアンス意識が求められます。
不祥事が報道されやすい公務員という立場で働く中で、自然と「ルールを守ることの重要性」や「信頼を損なわない行動」が身についたはずです。
これは、民間企業が求める社会的信頼の担保にも直結する要素です。
【実例公開】僕が職務経歴書に書いた「強み」
僕が実際に職務経歴書に書いていた「職務要約」を部分的に公開します。
参考にしてください。
■職務要約
約⚫︎年にわたり、⚫︎に対する許認可審査、相談・問合せ対応、⚫︎に係る条例や基準の策定といった⚫︎に関する業務に携わってきました。
庁内関係部署との対内業務だけでなく、民間企業等との対外業務の経験も豊富に培っています。
現在は課長代理として、メンバーのマネジメントや育成も手がけています。
■活かせる経験・知識・技術
・内外との豊富な調整経験
・相手の特性等を踏まえた説明力、説得力
・法令への知見(⚫︎関係規定に基づく指導に8年携わり、⚫︎関係条例の改正業務も経験)
・工程管理、タイムマネジメント
・マネジメントスキル(2021年より課長代理として部下を指導)
まとめ:あなたにも転職で活きる強みはある
「スキルがない」と思い込んでいるだけで、実際は多くの経験が価値ある“スキル”になり得ます。
まずは自己分析を通じて、公務員として培ってきた経験を言語化してみてください。
自己分析は、強みを見つけて言葉にするためのプロセス。
難しく考えすぎず、これまでの経験をゆっくり振り返ってみるところから始めてみてください。
最初の一歩は、不安がつきもの。
でも大丈夫。
一つひとつ、自分を見つめ直していけば、きっと「自分にもできることがある」と思えるはずです。
以下の記事で、「【転職したい公務員必見】自己PRの書き方」について、解説しています。
よろしければ、こちらも併せて読んでみてください。
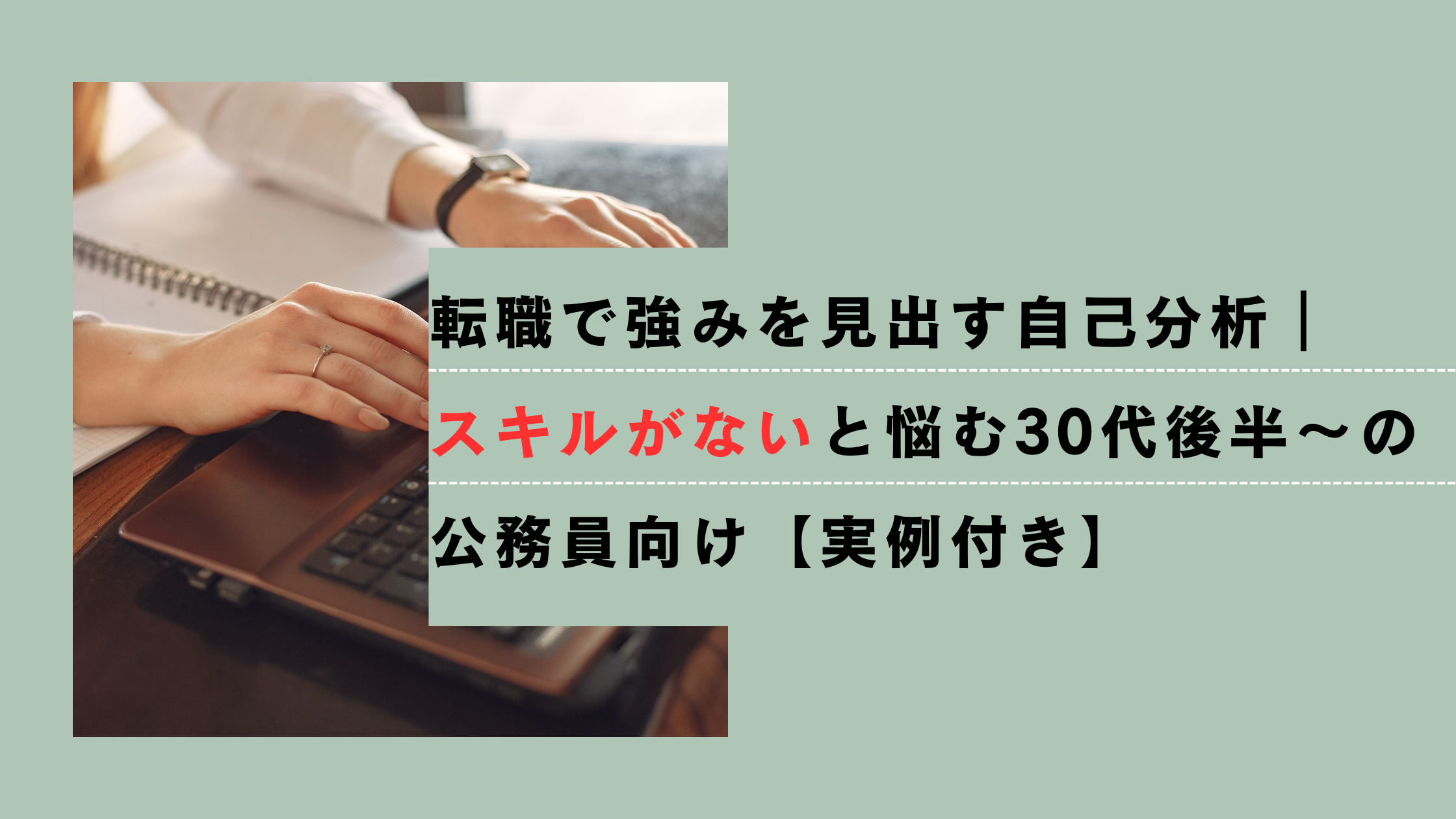
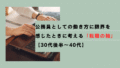
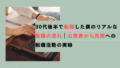
コメント